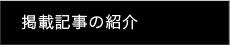第1回:戦国武将が現代にいたら
戦国武将ブームらしい。勇猛果敢な戦国武将が部下に的確な指示を与え、敵を蹴散らす。
武将の権限は絶対であり、みな命を懸けて主君の命令に従う。このようなドラマを見れば、
戦国の世と企業経営の違いはあれど、同じリーダーとして憧れを抱くかもしれない。
しかし、現代の戦闘は随分と様子が変わってきている。例えば、最強を誇る米国陸軍では、
兵士はトップの命令に必ずしも従わなくてもよくなっている。ロケット砲を発射するという重い権限でさえ、
末端の兵士に委譲されているのだ。これは、現代の戦闘がゲリラ戦、テロ戦という予想がつかないくらい目まぐるしく状況が変化する環境の中で行われるからだ。
トップにも現場で何が起こるか正確に予測することはできない。
また、現揚の連絡を受けてから、トップが判断し、現揚に命令を届けていたのでは、状況は既に変化してしまっている。
それに比べれば、戦国の合戦はのどかだった。
実は企業経営の場でも同様の変化が起こっている。少し前までは、カリスマ経営者が的確な指示を出し、
社員は忠実にそれを遂行することで成果を生むことができた。
しかし、それはマーケットそのものが拡大している幸せなビジネス環境下だからこそ機能していた現象だ。
なぜなら、現在のような成熟した環境下では、いくらリーダーとはいえ、的確に正しい手を指示することは難しいからだ。
刻々と状況が変化する環境では、米国陸軍の兵士と同様に現場が自律的に考え行動することが不可欠となる。
しかし、それを実現するにはリーダーが変身することが絶対条件である。今までのように、リーダーたる自分がすべてを決定し、
すべてを命令することが当たり前、では現場の自律性は育たない。
ところが難しいことに、権限を手放すことは、時に、リーダー自身の欲求充足を阻害する。
人々の上に君臨し人を意のままに動かすことは一種の快感でもある。残念ながらこのような君臨支配型のリーダーシップは、
リーダーの欲求充足はできても成熟したビジネス環境には適合しない。
そこで今後、この連載で、成熟したビジネス環境を乗り切ることができる「サーバントリーダーシップ」という考え方をご紹介していきたい。
「出会い」2009年8月5日号(経済界倶楽部事務局発行) 真田茂人
目次へ戻る 第2回:カリスマリーダーは何故少なくなったか