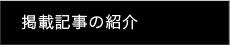第2回:カリスマリーダーはなぜ少なくなったか
リーダーと言えば一般的に織田信長や坂本竜馬、勝海舟あるいは松下幸之助や本田宗一郎などをイメージする人が多いだろう。
いわゆるカリスマ型のリーダーである。現代にはこういったカリスマリーダーは少なくなった。なぜだろうか?
別に現代人が幕末や昭和初期に比べてレベルが低くなった訳ではないだろう。
時代はその時代に必要なリーダーを生み出す。現代はカリスマリーダーがカリスマでいられる条件が難しくなったからだ。
カリスマリーダーは未来を読んで正しい号令を出さないといけない。そして、その号令が正しいから、リーダーはカリスマでいられる。
ところが、現代のような成熟した社会ではそれは極めて難しい。だから、今の世の中にカリスマリーダーは数少ないのだ。
逆に、今成功しているリーダーの中には、カリスマとはむしろ対極的なタイプのリーダーが少なくない。
彼らはカリスマリーダーと違い、自分ひとりで結論を出そうとしない。結論を出す前に社員や現場の話によく耳を傾ける。
経営不振のホテルや宿をわずか2年で屈指の人気施設に生まれ変わらせた星野リゾートの星野社長は、徹底して従業員の話を聞く。
なぜなら、現場のことは社長以上に従業員が知っているからだ。
成熱した社会では社長であっても「これは間違いない」と言い切れる正解は存在しない。正解があったとしても、
その賞味期限は短く、すぐに変化してしまう。だから正解を知りたければ、常に現場の声に耳を傾ける必要があるのだ。
そしてカリスマリーダーはあくまで自分が主役であったが、星野社長をはじめとする非力リスマリーダーは現揚の従業員や社員を主役に据えている。そして主役たる従業員の成功を支えようとする。
こういったリーダーをサーバントリーダーという。この場合の「サーバント」は「使用人」という意味ではなく、
「主義や信条などに身を捧げる人」という意味である。
つまり組織のミッションやビジョン等を実現するために、それを推進する部下に、彼らが成功しやすいように奉仕するのである。
そういう意味では、松下幸之助はカリスマリーダーであると同時にサーバントリーダーであったと言えよう。
(2009年9月5日号経済界倶楽部事務局発行) 真田茂人
第1回:戦国武将が現代にいたら
目次へ戻る
第3回:事業を継続できるリーダーの資質とは