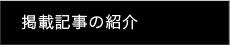第7回:マイクロソフト樋口社長のリーダーシップ論
前回の「出会い」でも紹介されたが、11月東京例会のマイクロソフト樋口社長のお話は大変有益であった。特にダイエ一時代のご経験には学ぶものが多かった。樋口社長の著書『変人カ』の中に次の言葉がある。
「ダイエーの問題は、右肩上がりの経済の下で成長してきた多くの日本企業が潜在的に抱えている問題だ。」顧客に目が向かず、自分の身を守ることに終始する内向き志向、というのが、氏がダイエーの社長に就任した頃に感じていたダイエーの問題点のようだった。
例えば、本部長会議で本部長が恥をかかないようにサポートする担当者が出席する。経営者は常に社員を何人も引き従えて行動する。社員同士の打ち合わせにも秘書がお茶を運ぶ。取引先やお客様に無意識のうちに横柄な態度を取る。
これらの原因を氏はカリスマ経営の遺産としている。経済が右肩上がりの時代には戦略が長持ちしたので、一人の優秀なトップの裁量で組織を牽引することができた。そのため社員が自発的に考えて行動するという文化が醸成されて来なかった。たとえ疑問を感じて発言しても、受け入れてもらえない。それどころか、トップの意向にそぐわないという理由で瞬時に異動させられることもある。強い権力に縛られたトップダウン経営の下では、小さな問魍でもトップ自身が決めるまでは誰も決めないという文化に染まっていく。
また、氏はこうも語っている。
「トップダウン緑営そのものが悪いのではない。トップダウン経営で好業績を統けている企業は少なくない。重要なのは、戦略転換が求められている時に社員一人ひとりの自発性をどこまで引き出せるかだ。環境変化が激しく、お客様のニーズも変わりやすい現在においては、トップ一人の器で企業の器が決まってしまうような体制はリスクが大きい。社員が知恵を出し合い、現場と本部が一体となって取り組まなければ、難局は乗り越えられない。そうした環境を意識的につくることが、これからのリーダーの役割ではないだろうか。」
これこそがサーバントリーダーである。
「出会い」2010年2月5日 (経済界倶楽部発行) 真田茂人
第6回:なぜ御用聞き営業から3千億円企業を作れたか
目次へ戻る
第8回:停滞企業が15年間増収益に転じたキッカケとは