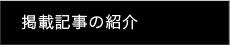第8回:停滞企業が15年間増収益に転じたキッカケとは
停滞していた状況を一転させて15年間増収増益を達成した歴史あるメーカーがある。以前は3つの強力な商品のお陰で高い収益率を誇っていた。ところがその結果、良く言えば堅実な、悪く言えば、決められたこと以外はしない体質が作られ、お役所的な硬直した組織になってしまった。当然、徐々に活力が失われていき、主力商品の優位性が失われるのと比例して企業力も衰えていた。
15年前、創業家の新社長が就任し、人事組織の大改革に着手した。目的は企業体質の転換である。改革の中身は、①人事制度改革②日常のコミュニケーション改革③社内イベントである。今振り返ると、人事制度改革の影響はさして大きくなく、最も影響が大きかったのは、日常のコミュニケーション改革だったらしい。
実施したことは些細なことばかりである。例えば、社長以下全員が肩書でなく「さん」やニックネームで呼び合う。特に目新しくはない。しかし、背後に深い意昧がある。肩書で呼び合うと部下は自然と上司に依存し、自己責任を放棄する。「社長」や「部長」が認めたんだから、失敗しても責任は社長にある、部長にある、と考える。そして、社長も部長もポジションパワーで人を動かす。そのため、自然と自分の意見が常に正しいと錯覚してしまう。上司が部下に君臨する形である。
ところが、「さん」で呼び合うとポジションパワーが働きにくい。部下は「社長」「部長」に依存せず、自己責任で考える。また、部長も「部長の俺の意見だから」と押し付けることができず、きちんと説明し、納得させることが必要となる。
結果として何が正しいかが議論され、アイデアそのものの中身が問われるようになる。良いアイデアであれば立場に関係なく採用される。その結果、この企業では新製品が年間5個から何と200個まで増えたという。
上司は部下に君臨する人ではなく、部下のアイデアや能力を引き出す人となったのだ。 これこそがサーバントリーダーシップである。
「出会い」2010年3月5日号(経済界倶架部発行) 真田茂人
第7回:マイクロソフト樋口社長のリーダーシップ論
目次へ戻る
第9回:セコムが世界的企業に発展した理由