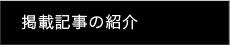第9回:セコムが世界的企業に発展した理由
先日、あるイベントの講演でセコムの木村昌平会長とご一緒した。私は議長を務めながら、木村会長のお話の迫力に心が震えた。
木村会長はガードマンとして入社しトップにまで上りつめた人物である。セコムは有人の警備事業からスタートし、今ではオンライン警備をはじめ、防災、テロ対鷲、病院経営、保険など様々な事業を世界各地で展開している。これらの事業展開はいかにすれば儲かるかという観点で行ってきたわけではないと言う。"あらゆる不安のない社会へ。困った時はセコムへ。"というミッションを愚直に突き詰めた結果として事業が広がっていった。
木村会長は創業者飯田亮氏から経営哲学を教わったそうだ。リーダーは常に自分の身を振り返る必要がある。いくら立派なルールやシステムを作っても、幹部の言動や後ろ姿、何気ない一言で組織は崩壊する。特にアフター5の言動にはリーダーの本音が出るので要注意だ。従業員はそれを見ている。
従業員への統制は極力しない。驚くべきことに予算統制もしないと言う。予算統制はビジネスチャンスを失わせるというのが理由で権限規定も設けない。
そして、経営者は捨てる勇気を持つべきだと言う。元々の事業であった巡回警備から撤退することで、オンライン警備の事業に展開することができた。そして、次にそのオンライン警備の専用線までも捨てた。まさに創遣的破壊である。
イノベーションとは技術革新ではなく、思想の革新である。自分たちで自分たちを否定するのだ。飯田氏は「俺はまだ事業意欲がギラギラしている。だから今辞めなければならない。自分を首にできるのは自分しかいない」と言って辞任し、木村氏に経営を預けた。
ミッションやビジョンを常に明確にし、それを推進してくれる従業員を信じ、彼らを統制するのではなく任せ、支援する。そして、自分自身が障害になると思ったら自ら身を引く。恐ろしいほどのサーバントリーダーぶりである。
「出会い」2010年4月5日号(経解界倶楽部事務局発行) 真田茂人
第8回:停滞企業が15年間増収益に転じたキッカケとは
目次へ戻る
第10回:岩崎弥太郎と坂本龍馬の違い