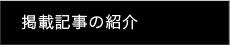第11回:旭山動物園の奇跡の復活と躍進の理由
先日、旭山動物園の小菅前園長のお話を伺った。旭山動物園の奇跡の復活と躍進は、本や映画のヒットにより大きな話題になったのでご存じの方も多いだろう。
小菅氏が管理職に昇進した時、市役所では閉園の方針が決まっていた。入園者は急激に減少していたが、動物園の職員は何とそれまで「客」の存在を意識したことがなかったという。動物のことだけ考えていれば良かったからだ。
小菅氏は最終的に「行動展示」という全く新しい発想の動物囲を作り上げ大成功するのだが、これは何も氏が1人で考え作り上げたものではない。アイデアが生まれ、形になったのには、小菅氏が行ってきた組織づくりに秘密がある。
小菅氏は様々な提案をしてきたが、その中に飼育研究会という勉強会がある。この勉強会の特徴は、動物の飼育に関して何でも話し合えるということである。この場を通じて、実はベテランでも分かっていないことがあったり、自分たちが固定観念に囚われていることも分かった。こうした経験から、お互いに正直に話し合い、より良くするために協力する風土が徐々に醸成されていった。閉園という危機に際しても「理想の動物園」について話し合えたのはその成果であろう。
しかし、理想の動物園を夢見ても予算はなかった。そこで小菅氏は「全員ができることをやる」という方針を掲げた。 皆、今まで動物のことばかり考えてきたので、マーケティングセンスがあるわけでも、ブレゼンテーションが上手いわけでもない。その状況で全員が自分の特徴を生かして、できることをするしかない。小菅氏の人の長所を生かそうという姿勢が、職員一人ひとりの才能を引き出した。
全職員が観客の前で動物の説明をすることになった時、ある話が苦手な職員が始めたのが、動物が餌を食べる瞬間を分かりやすく見せることだった。これが行動展示という発想に繋がったのだ。
小菅氏は言う。「組織改革にスターはいらない」。 カリスマが強烈に先導するだけが組織改革ではない。メンバーの長所を上手く生かして、活躍の場を与える。こういったサーバントリーダーも組織改革には必要なのだ。
「出会い」2010年6月5日号(経済界倶楽部事務局発行) 真田茂人
第10回:岩崎弥太郎と坂本龍馬の違い
目次へ戻る
第12回:世界のソニーを創った盛田氏の至言