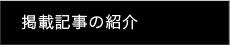第13回:無印良品がV字回復できた理由
先日、無印良品を展開する良品計画の松井会長にお会いした。
良品計画は2000年から業績が悪化。01年には急激な業績低迷に陥った。株価も急落。時価総額が75%も減少した。そんな状況下で01年に松井氏が社長に就任し、翌年に増収増益を達成。その後見事にV字回復を果たした。なぜV宇回復ができたのか。それは松井社長のリーダーシップスタイルと大いに関係がある。
就任して、松井氏はまず全国にある全ての店舗を回った。全ての現場を見て、店長と話し合い、夜は共に飲み、交流を図った。現場の声を聴いて問題を明らかにしようとしたのだ。
業績低迷の大きな原因のひとつに“大量の在庫”があった。バイヤーが買い過ぎるのだ。凡庸な経営者ならバイヤー達を集めて責任を追及し、反省の弁を要求するだろう。罰を与えるかもしれない。
しかし松井氏は「問題を人災とすれば、手が打てない」と言い、真因を探った。それは各バイヤーが使っている帳票の存在にあった。上司から見えず、仕入れに関する情報が経営陣にはタイムリーに入って来ないのだ。 松井氏は、全社共通のフォーマットを導入してそれを解決した。
問題を人災として対症療法に終始していては解決しない。また、個人が頑張って解決するのでは積み重なっていかない。経営の仕組みが変わらない。仕組みを作って解決すべきである。「現揚で起きている問題を組織や仕組みで解決するのが経営者の仕事ですから」と松井氏は語った。見える化、シンプル化、共有化をベースに仕組みを構築していくのだという。
代表例が『MUJIGRAM」。これは無印食品の店内業務、売り揚づくり、経理や労務管理など、良品計画のあらゆる業務に関するマニュアルである。最もマニュアルと縁遠い文化であった良品計画に業務の見える化、共有化の仕組みを導入したのだ。
サーバントリーダーシップの10の特性として『概念化』と『先見力』が挙げられている。会社の危機に際して、問題の真因を発見し、仕組み化していくのがサーバントリーダーの働きである。
「出会い」2010年8月5日号(経済界倶楽部事務局発行)
第12回:世界のソニーを創った盛田氏の至言
目次へ戻る
第14回:サッカー日本代表岡田監督が望んだチーム